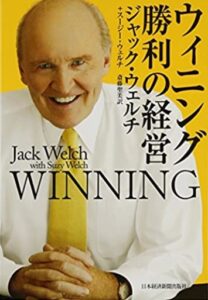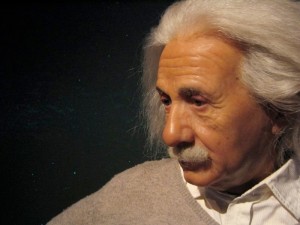新規事業の作り方とおすすめ本9選
新規事業の成功方程式
チーム×戦略×努力×運=結果
運は努力によってつかめる確率が変わる。努力は良い戦略なしでは道を逸れる。戦略は人が実行して成立する。
新規事業の責任者の役割
強いチーム作りと戦略を練り、人を動かして目標を達成する。
新規事業を成功させる作り方
- 1.優秀な人材をリーダーにアテンドできているか
- 2.強いチームをスモールに構築しているか
- 3.意思決定スピードを上げる環境になっているか
- 4.顧客の声を聞く態勢はあるか
- 5.市場の拡大を何度も確認できているか
- 6.スピードスピードスピード
1.優秀な人材をリーダーにアテンドできているか
新規事業を立ち上げること、そこから売り上げをつくって黒字化していくことは超絶大変です。それを知っているのにも関わらず、会社の中心人物を出したがらないケースは多く存在します。
理由は簡単で、既存の事業が崩れてしまうのが怖いから。新規事業を成功させたい、そう本気で思っているのであれば、必ずエースを投入しましょう。
優秀な人物でなければ、新しいことを成し遂げることは絶対に出来ません。上手く行かなかった時に、絶対に後悔します。あの時、あのヒトを抜擢していれば…なんてことに。
2.強いチームをスモールに構築しているか
リーダーを決めたら、次はチームビルディングです。
リーダーの強みをより引き伸ばせる人物や弱みをカバーできる人物をチームに投入しましょう。ポイントは、組織を小さくつくることです。
初めから大きくしない理由は金銭的損失はもちろん、「組織風土づくり」「意思疎通速度」「人間関係」においても、小さいほうが強い動きができるからです。
3.意思決定スピードを上げる環境になっているか
新規事業は失敗と改善の積み重ねです。その改善のスピードを高めることができなければ、顧客の信用は勝ち取れません。
事業責任者だけで判断できる環境を構築するのはもちろんのこと(神々の声が発生しないようにする)、できれば現場レベルである程度の権限を持てるようにしましょう。
意思決定速度をたかめ、失敗を経験し、それを改善する回転数を高めることで自ずと事業成功確率は高まります。
4.顧客の声を聞く態勢はあるか
事業で思い描く製品・サービスが、市場が合致しているのかを顧客にヒアリングしましょう。
新しい事業やプロジェクトがスタートする前に、顧客層を想定し、顧客が必要としているかどうかを聴きましょう。事業開発後も絶えず顧客の意見を聞ける態勢を構築すること。
顧客に聞くべき最も大事なことは「それ、お金払ってでもほしいですか?」です。
満足度や不便解決の目線だけで顧客にヒアリングすることはおろかです。事業運営で重要なのは売上。お金を払う顧客がいるかどうかということを忘れてはいけません。
5.市場が拡大しているか何度も確認
新規事業は、「市場が大きい」もしくは「市場が急拡大している」ところでスタートさせるのが前提です。
事業構想時、事業構築時、事業運用時、絶えず市場動向をチェックすべきです。
拡大していると思っていた市場を再確認し、停滞が見えるのであればピボットや撤退を考えましょう。市場の大きさは情熱では覆せません。
市場を掴むことが難しければ、業界トップから3番手までの企業情報を確認しましょう。
上場企業であれば、すべてのステータスがオープンになっているため、正確な情報を集めることができます。その企業3社とも業績が低下しているようであれば事業の生末も見えています。
6.スピードスピードスピード
何よりも重視すべきはスピード。
意思決定、新しい動き、改善。思考よりも試行を大切にする組織をつくりましょう。完璧を求めてはいけません。多少の失敗はケセラセラ(なんとかなるさ)するチームであり続けましょう。
エネルギー=質量×速度²という物理法則通り、速度をだすことで組織にエネルギーが連続的に生まれ続けます。
絶えず確認したい「執着」と「情熱」
- ・執着のある先導者がいるか
- ・顧客を情熱的にできるか
この2つのうち、どちらかがしっかりしていないと事業運営は成立しません。
執着のある先導者がいるか
執着=継続的な情熱です。
自分達が勝負している市場や事業、組織の人材に対して、成功を信じている人物がリーダーになっているかチェックしましょう。リーダー自身であれば自分に問いかけるべきです。
成功までのプロセスの語り部となり、次々と語り部を増やせる先導者こそ事業責任者のあるべき姿です。
顧客を情熱的にできるか
アップルは、商品を熱狂的に指示するユーザーをエバンジェリストに昇華することで、イノベーターとアーリーアダプターを味方につけました。
ユーザーが熱狂的、反応的、反射的、そして中毒的になるような商品づくりや仕掛け作りを考え続けましょう。
| 【イノベーター理論】商品購入の態度を新商品購入の早い順に五つに分類したもの 1.イノベーター:冒険心にあふれ、新しいものを進んで採用する人。市場全体の2.5% 2.アーリーアダプター:流行に敏感で、情報収集を自ら行い、判断する人。他の消費層への影響力が大きくオピニオンリーダーとも呼ばれる。市場全体の13.5% 3.アーリーマジョリティ:比較的慎重派な人。平均より早くに新しいものを取り入れる。市場全体の34.0% 4.レイトマジョリティ:比較的懐疑的な人。周囲の大多数が試している場面を見てから同じ選択をする。市場全体の34.0% 5.ラガード:最も保守的な人。流行や世の中の動きに関心が薄い。イノベーションが伝統になるまで採用しない。伝統主義者とも訳される。市場全体の16.0% |
新規事業について体系化されている本9選
 |
スタートアップ・マニュアル ベンチャー創業から大企業の新事業立ち上げまで計画が大事じゃないよ、スタート後の柔軟性が大事だよ。小さく始めることでいろいろうまくいくんだよ!ってことが書かれています。 |
 |
スタートアップ・ウェイ 予測不可能な世界で成長し続けるマネジメント大きく考え、小さく始め、すばやく成長する。リーンスタートアップの原則をチームとプロジェクトの動き方に具体的に当てはめて記述されています。 「行動しやすさ、わかりやすさ、チェックのしやすさ」「ピボットのタイミング」「チームの基本行動統一のためのポリシーづくりの重要性」など新規事業のスタート、グロースどちらにも焦点があたっていて、だれにでも飲み込みやすい内容になっています。 |
 |
競争優位の終焉 市場の変化に合わせて、戦略を動かし続ける僕的に超絶良書。「もう世の中は変化激しすぎだから、優位性とか瞬時になくなるし、一つの戦略に頼ってるんじゃ、すぐ潰れんじゃん?!」が当書の主張。 オプション思考(常に選択肢を豊富にもち、多くの可能性を考慮することで、迅速な対応を繰り出していく考え方)を思考フォーマットに、「戦略も戦術もめちゃくちゃ変えていいんだよ~」「持続的競争優位なんてないんだよ~」「アジリティは現代ビジネスの最強武器だよ」ということが痛快に書かれてます。表面上の差別化とか何にも役に立たない! |
 |
ブリッツスケーリング LinkedInの共同創業者であり、Airbnbのボードメンバー、さらにはFacebookなどにエンジェル投資をしているシリコンバレーの著名投資家リード・ホフマンの書。リーンなんて最初だけで、そこからはハイリスクを抱えて電撃的に規模拡大しろ!というグローバルビジネスの本質が書かれている。 |
 |
経営の失敗学 (日経ビジネス人文庫)変化が激しい時代だからこと、失敗学を体系化して覚えることで、ミスを減らしてこうぜ!結果的に成功確率上がるじゃん!ということが痛快に書かれています。 |
 |
マーケティングとは「組織革命」である。 個人も会社も劇的に成長する森岡メソッドマーケティング若者会のカリスマ森岡さんの最新作。タイトルからしてすでに本質的。組織の血がうまくめぐるようにしていないとマーケティングなんて出来っこありません。 組織のトップ層が見るべき前半のパートは、マーケティング以外にも多くの組織学が目から鱗。後半は事業提案者側が会社とどう戦うべきを密に書かれています。人々の理想行動を増やすための「見える化」「仕組み化」「評価」めっちゃ勉強になりました。 同著の「USJのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのか? (角川文庫)も最高のおすすめです。 |
 |
世界No.1コンサルティング・ファームが教える成長のルール個人の成長学が掛かれていますが、事業成長にも共通する内容満載。「毎日1%成長する」「注力すること、そしてやめること決める」「意思決定を連打する」「思考の速度よりも試行の速度を超重視」「自分の得意分野以外は他人に任せる」など金言かよ!と思うことが書かれてます。また、第5章の『人間関係構築力を磨く』もコミュニケーション下手な人にはおすすめの内容です。 |
 |
新・あのヒット商品のナマ企画書が見たい!とにかく多くの資料を見たい方におすすめです。頭の中にプレゼン資料の『型』がはいっていればいるほど、資料作成ははやくなっていきます。企画書のフォーマットを吸収するのには便利です。 |
 |
企画書実践事例集[完全版]企画書作成のための参考本をたくさんだされている高橋さんの本です。企画書を作成するまでの工程が事例で書かれているためとっつきやすく、手元に一冊あると困った際に取り出して解決できることが多々あります。 |
印象に残ったフレーズやセンテンス
- ・ゼロには、いろいろと創造する余地があるが、小さな数字は将来的にそれが大きな数字になりうるのかという疑問を招く。本来であれば、現実に一晩であっと驚く大成功を収めるサービスがるのにも関わらず、小さな数字が計測されると、大成功の夢に冷水を浴びせることになる。データをとることは重要だが、それでも前に向かって前進し続ける意思が必要
- ・成功とは機能の提供ではない。顧客の問題解決こそ成功と言える
- ・事業計画は仮説から始まる。仮設を前提に戦略を立て、すぐに仮設の検証を行う必要がある
- ・最初のリリースは80%満足できるものであれば充分。顧客に合わせて100%を目指す
- ・スタートアップには3つのしやすさが重要「行動しやすさ」「わかりやすさ」「チェックしやすさ」
- ・ウェブ・モバイル市場の規模をPV、DL数、表示回数、滞在時間で表現する人がいるが、最終的に重要なのは売上高。お金を払う顧客がいるかどうかである
- ・製品と市場がフィットしているのか、何があればフィットするのか、それを顧客に聞くのだ
- ・主要ターゲット顧客の属性とアーキタイプを理解し、主要ターゲット顧客に効率よくアプローチできるよう行動を理解する必要がある
- ・その事業でスケールすると、会社が大企業になるのか
- ・営業させる前に、営業ロードマップを描け。そして営業状況は必ず把握すること、ここを任せきりにしてはいけない
- ・初期のチームは2人が最強。4人以上は避けろ
- ・画期的なアイデアが生まれるのを待つな
- ・「当社でやる意義」は問うな
- ・プロジェクトメンバーをいきなり新規事業専任にするな
- ・朝令暮改を受け入れる変化に強い組織風土をつくる
- ・組織とは「一人一人の能力を引き上げる装置」。組織力とは「個人技とシステムの掛け算」。60点の人間に90点を取らせる組織が良い組織
- ・マーケティングは部分最適では最高点には到達しない。部位ではなく、繋がりに注目する
- ・必要な組織構造は企業(事業)の成長過程で変わる
- ・「選択と集中」、たまに「大きく拡散して選択」を繰り返す
- ・何度も短期間で『着想→仮完成→自ら顧客の声に合わせ評価→ブラッシュアップ』を繰り返す必要がある
- ・スタートアップの考え方は、既存事業の生き返りにも適応できる
チームビルディングにおすすめの本7選
 |
こうして、チームは熱狂し始めた。マネジメント層には圧倒的にお勧めしたいのが、当書籍です。これは、個人的には超ヤバイ! タイトルは苦手です。なんか暑苦しそうで...ただ、中身は、想像と全然違います。論理的で再現性の高いチームのつくり方がリアルに描かれています。営業チームのビルディングや活性方法など、マネージャーが躓きがちなポイントが細かに書かれています。超良作。 |
 |
完訳 7つの習慣 人格主義の回復どんなリーダーについていきたいか...それは成果を出すリーダーです。 しかし、それ以前に人格ある人物が、人を惹きつけます。人格は変えられるし、人格は良くすることが出来るので、部下に好かれない人にはおすすめしたいです。 |
 |
絶対達成する部下の育て方――稼ぐチームに一気に変わる新手法「予材管理」マネジメント系の本って、思想っぽい本はたくさんあるんですけど、どうすれば目標達成させられるかの具体的ノウハウが書かれている本ってないんですよね。 この本は、そういったウヤムヤにされている部分を、実践形式で詳細に書かれています。 マネジメントは論理と感情と向き合うことで完成していきます。その論理部分をマスターしたいのであれば必ず読むべきです。 |
 |
今いる仲間で「最強のチーム」をつくる 自ら成長する組織に変わる「チームシップ」の高め方 コンサルティング業界で超尊敬している池本克之さんの著作。 ぼくはマネジメントの最重要項目として「対話」を掲げているのですが、その考え方の基本を教えてくれた本です。 どんな状況においても成果を上げられる、そんな組織をどうやってつくるのかが把握できます。 |
 |
人を動かす 文庫版 歴史的ベストセラー。読んでて当然系。 人を動かすために何が大切で、どう動けば人が動くのか。その原理原則がこれでもかと書かれています。 人生の中でもっとも見返した本。 |
![影響力の武器[第三版] なぜ、人は動かされるのか](https://www.correc.co.jp/mahoken/img/common/1x1.trans.gif) |
影響力の武器[第二版]―なぜ、人は動かされるのか こちらも歴史的名著ですね。 影響力の武器...というタイトルが若者に響かない気もするのですが、影響過程に関する心理学的知識が圧倒的に身に付きます。 社会心理学や顧客心理学なんて浅はかなことばでは表現できないですが、とりあえず誰でも見とけって本です。 |
 |
憂鬱でなければ、仕事じゃない管理職という職位はとかく憂鬱になりがちです。 数字のプレッシャーが永遠に続き、新人の面倒も見ねばならず、上司の意見にもついていかなくてはいけない。 しかも、どんどん褒められない立場になっていく...でもね、憂鬱じゃなければ仕事じゃないんです。 |
新規事業の成功確率は0.3%
新規事業の成功確率は、0.3%と言われるケースが最も多いです。日本で最も新規事業のノウハウがあるリクルート社ですら、
- 1,000件の新規アイデアがあり
- 事業化フェーズに進むのは2%の20件
- 黒字化に到達するのが15%の3件
- 参考:新規事業生む組織とは?リクルート名物制度の秘密
と語っています。1,000あっても3つしか成功しないため、リクルートの新規事業開発室長の麻生要一氏も書籍新規事業の実践論のなかで、新規事業は千三つ(センミツ)であることを話しています。
とはいえ、新規事業の成功確率説は大概いい加減なもので、10%の成功確率があるとも言わています。
※おそらく10%の出元はユニクロ柳井正氏の書籍『一勝九敗 』であり、その後40の新規事業を生んだDeNA流リーンインキュベーションなど新規事業に挑戦する有名企業がそれに近しい数字を出していたために広まった
成功とは異常なこと(余談)
 |
 |
サイバーエージェント藤田社長のビジネスの成功確率の話です。新規事業を1つ成功させたからといって「再現性のあるフローが確立できた」「事業案や企画立案は上手になった」などとうぬぼれてはいけません。
確率は不変であり、成功に慢心すると一瞬で足元を救われます。
事業開発や事業再生の関連記事
関連記事
伝説の経営者ジャック・ウェルチの名言
圧倒的な経営手腕から「伝説の経営者」や「20世紀最高の経営者」とよばれたジャック・ウェルチ。 1981年から2001年にかけて、ゼネラル…
頭が良くなる本をご紹介!お金持ちは読書する
頭が良いと言われる人には憧れちゃいます。頭が良ければキャリアを選べ、人生を有利に運べます。 当記事では、頭が良いと言われる人の共通項と、…
マネジメント本おすすめ24選
管理職の悩みは一生絶えることがありません。毎日予期しないことが起こり、上司の求める事は熾烈を極め、部下の我儘は常に意表をついてくるため、そ…